その部屋には白い霧のようなものが張っていた。
あたり一面を覆うそれは、その部屋の今の主にとっては
ここちのよいものだった。そして、自らの邪魔となるであろう
存在をその部屋に元いた者の記憶から知ることとなる。
「ボク、もうこの街にはこれないと思うんだ・・・」
悲痛な面もちでそう告げるあゆあゆ。俺はそれに妙な違和感を
感じた。この話でこんな悲しい場面があるはずはないのだ。
「でも、おまえの足でこれるんだから国境こえた程度のところにいるんだろ?」
「・・・」
だが、あゆあゆはなにも告げず去っていく。
俺はその後ろ姿をストーキングしてみることにした。
しばらくついていくと、あゆあゆはぴたりと歩みを止め大きく息を吸い込んだ。
まるで何か鬼門でも通る覚悟のようだ。そして意を決してはいった先は・・・
病院。
俺も気づかれないようにあわてて中に入る。その瞬間、
頭に白いもやがかかったようになってしまった。
「あれ・・・俺はなにしにここにきたんだ・・・?」
なぜ、ここにいるのだろう?誰かを追いかけてきたのだがそれを
思い出せないのだ。今まで誰に見つからないように追いかけてきたのだろう?
隠れる必要があるのか?俺は自分の行動に疑問をもったため堂々と歩く。
すると見知らぬガキが話しかけくる。
「ゼロワンくんっ!」
「誰だてめぇ。」
なぜ、俺の名前を知っている?このガキ・・・背中に羽なんぞはやしやがって・・・
「ボクだよっ!くだらない冗談いってる場合じゃないんだよっ!」
「・・・」
怪訝そうな顔をしていたんだろうな、俺は。その顔をみてそいつは顔を曇らせ
どこかへと走っていった。なんとなく気になったので俺もその後を追うことにした。
「ボクの存在が・・・薄れている・・・永遠の世界に浸食されているの・・・っ?」
そう思うとボクの足は止まらなかった。一刻も早く元の体に戻らなければ、
永遠に意識不明のまま過ごすことになってしまう。病室は・・・ここだ。
バタンッ。
激しくドアをあける。かなり走ったためか息が荒くその静かな病室に響く。
いや、そこは病室なのだろうか?カーテンがしめっきりになり、
あたりに白い糸のようなものが張り巡らされている。すくなくとも、
2週間前の病室とは様子が大きく違っていた。
「ふ、ふふ、ふ・・・・ようこそ、私の巣へ・・・」
「あなたは・・・・誰・・・!?それにここはボクの病室だよっ!」
その人は黒い髪をなびかせながらこちらをみている。
風もないのに、髪がなびく・・・?
「娘・・・あなたは、人外のもの、というのを知ってて?」
黙って頷く。
「なら話は早いわね・・・それよ。」
つまるところ、敵、というわけのようだ。
ボクはそう思うや否や全力でそいつに突進した。
ドンッ!ぷちゅる。
何かを踏みつぶす感触。よくみると足下に一匹の蜘蛛が奇妙な液体を
吐き出しながら息絶えていた。
「この・・・小娘がァァァァァァァ!!」
「あれ・・・そういやあのガキ・・・どっかで見覚えが・・・」
俺は突如わずかに頭にかかっていたもやがはれた気がした。
あまりの早さに見失ってしまったあいつに見覚えがあるきがしてきたのだ。
とりあえずあちこち見て回る。1階、2階、4階・・・
だがどこにもそいつの姿は見あたらなかった。4階へとあがる階段の踊り場に
蜘蛛が巣を張っていたので殺しておいた。
病院に蜘蛛が巣はってるなんて不衛生だな・・・
その蜘蛛を殺した瞬間から、なぜ3階は調べないのか、という疑問が浮かんだ。
そしていつの間にか一人の女性を知っていた。さっきまで
当たり前の事実だったのだ。知っていて当たり前。
「初音って・・・誰だ・・?」
ひらさかはつね・・・いつの間にか埋め込まれていたこの単語。
そしてますます気にかかるあのガキ・・・俺は3階へと向かった。
3階・・・それは暗黙の了解ににたようなものだった。
3階はいかないという約束。それがはつねの結界がきめた決まり事。
「あゆあゆあゆあゆあゆあゆあゆあゆあゆあゆあゆ」
そいつに無数の拳撃を浴びせる。が、それは謎の糸によって
直前で防がれてしまう。
「人間如きが・・・・小賢しい真似をッ!」
そう、いつの間にか知っている。こいつは初音という。ひらさかはつね。
はつねは手を一振りすると巨大な爪へと変貌させた。
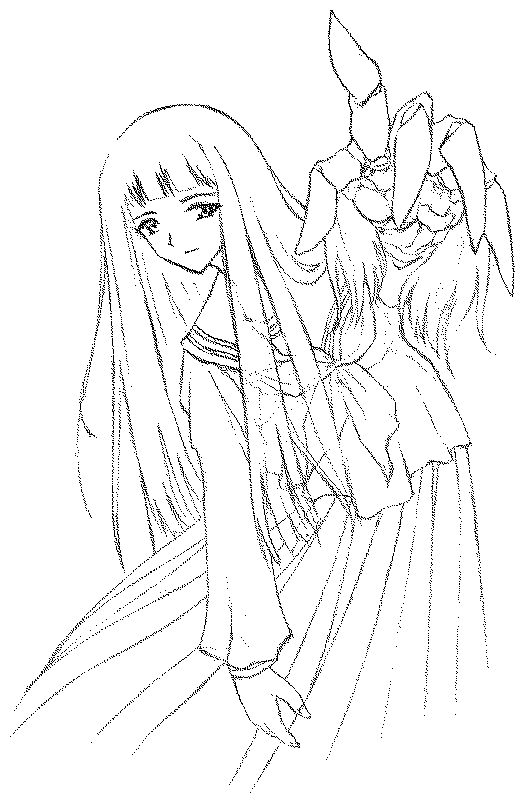
「この爪であなたのはらわた引きずり出してやるわッ!
生娘のはらわたはさぞかし美味なのでしょうねぇッ!」
いってることが、やばすぎる。その爪が目前へと迫る。
ブゥン!風が恐ろしい音を上げ響く。
「ふ、ふふ、ふふふふふ・・・・」
それはボクの頬をわずかにかすめ爪を血塗れにしていた。
はつねはそれは舌でおいしそうに舐めている。
「惜しいわね・・・あなたのその強い精神・・・
贄としてぴったりなのに・・・私に牙をむいたばっかりに・・・」
こいつは、やばい・・・ボクはこれが限界だ。だがはつねには
まだ余裕がある。このままでは、ヤラレル。
そしてはつねの爪がボクの頭上へと振り下ろされる。
「ここか・・・」
俺は扉を目前にしてわかってしまった。ここだけ空気の流れが違うのだ。
妙な空間がこの先に広がっているのはわかる。俺は固唾を飲んで
そのドアを開いた。
「なんだ・・・この空間は・・・」
おきまりの台詞をはいてみるがまったくその通りなのでこれ以上いいようが
ないのだ。あたりに張り巡らされた蜘蛛の巣。その中央に糸にぐるぐるまきに
されているどこかでみたガキ・・・・
「おい・・・・あ、えーと・・・なんていう名前だったかな・・・・」
「ようこそ、永遠の世界へ・・・・」
背後にたっていたはつねが耳元でささやく。
「永遠がほしくはない?」
「永遠の快楽に身をゆだね。」
「永遠にみなから忘れ去られるのよ!」
俺はその言葉を聞いたときとっさに壁をぶち破り脱出をはかっていた。
本能のなせる技だ。意図したものではない。
まさかはつねも壁をぶち破るとは予想もしていなかっただけに反応が
遅れた。だがはつねはほくそ笑む。
「すでにあなたは私の贄となっているのよ・・・戻っておいで・・・」
「はぁ・・・はぁ・・・あいつは・・・人外だ・・・」
俺は家へと戻った。そして二階にあがると見知った顔が出迎え・・・あれ?
「誰だ?私の家へと無断で上がり込む愚か者は・・・」
「なゆなゆ、今は疲れてるんだ。ほおっておいてくれ・・・」
俺は無視して階段をあがろうとするも一向にそこから先へは進めなかった。
「ばかな・・・確かに階段を上っているはずなのに・・・!」
「私の知らぬものを上げるわけにはいかんなぁ・・・」
その表情をみて俺は悟った。本当に俺のことを忘れているようだ・・・
なゆなゆのぼけだろうか?と、そのとき、背後に気配を感じる。
「おや・・・お客さんですか?」
「違うよ。不法侵入者だよ。」
「戦慄の侵入者ですね。」
「うん。」
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ・・・・
俺はその場から逃げ出した・・・いったいどうなっているのだ?
俺の存在を忘れているというのか・・・?
そこに家に一人の少女が帰ってくる。アサッシンのまことだ。
だが、家からでてきた俺をみても攻撃することもなく入っていく。
「恨みが晴れたのか・・・?」
俺のその嘆きにも聞こえる声すら聞こえず・・・
「ピアニッシモッ!俺だ!ゼロワンだッ!」
「不審者というのはな・・・実は寂しがりやなのではないか、
と私は思うのだよ。つまり、私の前に立ちはだかる勇気があるのか
ってことを聞いてるんですよッ!これがッ!」
ドガァァァ!足下に吹き上げる火を間一髪でかわす。
学校のいつもの場所でピアニッシモを見つけ話しかけた結果がこれだ。
不審者か・・・俺はふと物陰に気配を感じた。
そいつはさっきからじっとピアニッシモのことをみつめている。
俺は用心しながらそこに近づいていく。
「最弱ピアニッシモ・・・こいつがいたのでは私の復讐は
なしとげられない・・・ッ!?あ、あははーっ、誰ですかーっ?」
後ろにたつ俺の姿に気がついて語調が突然変わる。どうみても
おかしい。普段なら「さゆりの背後にたつとはいい度胸してますね~。」
てな感じで殴られるが今回はそれがない。魔法と称するものを発する
ステッキも隠している。ばればれだが。
「いや、なんでもない・・・」
俺は肩を落としその場をあとにした。
今の俺は誰からも忘れ去られ孤独だ。
そう、まだあいつがいる。俺と同じ状況のあいつならもしかしたら・・・
そう思うと俺は病院へと駆けていた。
病院の前の横断歩道、信号が赤から青に変わる。その先に俺は見た。
羽をはやした少女、今なら思い出せる、あゆあゆの姿を。
俺はゆっくりと歩道を渡りだす。そして向こうもゆっくりと歩道を渡りだし、
素通りした。
俺は思わず走り出そうとした。孤独に耐えきれなくて。
だがそれは背後からのびる手によって遮られる。
突如背後から抱きつかれたのだ。
「やっと・・・みつけた・・・!」
孤独から解放された俺は涙をにじませながら振り返る。
俺の存在を忘れてなかったんだな・・・
そこには優しい微笑みをたたえる、
はつねの姿があった。
「永遠は、あるよ。」
ぱさ・・・乾いた音が横断歩道に響いた。
あたりのクラクションの音が遠い。はつねは残った帽子を
一瞥すると病院へと帰っていった。
私は突然胸がとても苦しくなった。
殺したくて殺したくて焦がれている人を取り上げられたような気分・・・
それは自らの存在意義を取り上げられたような・・・過酷で切なくて、
耐え難い衝動。それに駆られた私は本体から抜けだし街を疾走していた。
「これは・・・どういうことだ・・・?」
と、その時持っていた携帯が鳴り響く。私はそれを手に取り通話を始める。
「ああん?どうもこーも、こいつは帽子だけ残してきえてるんですよっ!
ちょろい精神の持ち主だったってぇことじゃないんですかっ!以上ですっ!」
私は荒々しく、携帯の電源を切るとその帽子をまじまじとみる。
するとまるで何かに押しつぶされたような後がたくさんあるではないか。
推測すると・・・
「押しつぶされて殺された・・・?これをやったのはなゆなゆ・・・
貴様なのか・・・?だとしたら、これは願ってもない事ですよっ!」
期待に打ちふるえながらその帽子をひろう。すると背後に一人の老婆が
現れる。
「ああ、お婆さん。私は今用事を終えたところなんです。
つまり、疲れてるっていってるんですよっ!これがっ!」
「いえいえ、あなたが暇を持て余したら周りに被害がでてしまうので。」
老婆が目を見据えて言い放つ。
「そんなこというんですか・・・そういえばあなたは近接戦闘タイプですね。
少しは歯ごたえがあるかも・・・どうです?ド付き合いしてみませんか?」
「わしも命は惜しいのでね・・・遠慮させていただきますよ。」
「残念です。」
そういうと老婆は先ほどの用事を聞いてきた。
「ああ、これを管理しておいてもらえます?」
私はその帽子をほおる。老婆はそれをみて動揺する。確か、一緒に住んでいたらしい。
「では用件を伝えます。この近辺で未知数の力を持つ人外なるものが存在するらしいのです。
それの調査、危険と判断されたのなら打倒を検討する、といった内容ですが・・・」
「ふぅ・・・だいたいそういうのって見かけ倒しが多いんですよね。」
率直な感想を述べる。老婆は嫌な顔ひとつせずそれを聞き流す。
「あなたの手に掛かればこそ安全だということをお忘れなく・・・」
「その台詞、ちょっと芝居がかってますね。」
私の嫌みを何事もなかったかのように受け流すとそれでは、と老婆は去っていった。
「人外なる者・・・私を楽しませてくれるんですか・・・?」
期待に胸を膨らませ私は飛翔した。とりあえずは情報収集が先決だ。
私は本体へと戻ることにした。
「まだ、贄が足りないわ・・・」
病室で一人の女性がうごめいている。その部屋に張り巡らされた蜘蛛の巣は
まるで幻想的な世界を醸し出すかのようにもみえなくはない。
「新たな・・・贄を探しにいくとしましょうか・・・・」
その女性、初音は自らの体に糸を収縮させる。するとそれは衣服となり初音を包み込んだ。
「今日は転校生を紹介する。」
教室に教師の声が響く。それにつられて教室の中へはいる初音。
ざっとあたりを見回す。強力なほどに精気を発しているのは・・・二人。
眼孔が二人とも異常なほどに鋭い。こちらの意図をまるでよんでいるかのように。
そしてその呼吸から二人は主従関係にあるのだ、と初音は悟った。
「ん、あー、そこが空いているな。よしそこに座れ。」
そこはかつてゼロワンが座っていた席。持ち主はもう、いない。
初音の世界、永遠の快楽に身を委ねる世界へととらわれてしまったのだから。
「よろしく、私はひらさかはつね。」
とりあえず無難な自己紹介を行う。
「私はなゆなゆ。はつね・・・さんて呼べばいいのかな?」
「姉様と呼んでくださいまし。」
「じゃあ私のこともなゆ様って呼んでくれる?」
「小娘が・・・・いきがるなよ。」
険悪なムードが突然漂う。後ろの席のその下僕にあたる人物がなだめる。
「まぁまぁ・・・私はかおり・みさか。よろしく、はつねさん。」
「かおり、さん?」
「ピアニッシモでいいわよ。」
「・・・じゃあ、そうね。私のことは姉様と・・・」
「姉・・様?その台詞は・・・心に届きすぎる・・・」
こいつら、おかしい・・・はつねは100余年の年月の間にこの世界が
どうなっているのか非常に興味をもったが聞きたくても聞けないことだ。
それは諦めるとしよう。それよりもこいつらの隙を見いださなくては・・・
隙を見いだし、食らう。贄にするのもよいだろう。だがこうも力が満ちあふれていては
こちらとて手を抜くわけにはいかない。とりあえず、この学校に結界を張ることにしよう。
病院に戻れば、力は回復できる。出し惜しみする理由などない。
こうして初音はなゆなゆとピアニッシモの二人に学校を案内させつつ結界を張るための
蜘蛛を設置した。これで初音がいない間も記憶を鈍らせることができる。
「では、ご機嫌よう・・・」
「さよなら、初音さん。」
「さよなら、ひらさかさん。」
表面上にっこりとほほえむ初音だが内心「この小娘どもが・・・なぜ姉様と呼ばない・・ッ!」
などと怒りに震えていた。だがそんなことより病院へ戻らなくては・・・
一刻も早く休息をとることが必要だ。結界は思った以上に初音の体力を奪っていた。
わずかに立ちくらみを覚えながら初音は病院へと帰っていった・・・